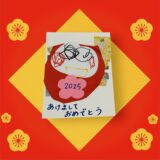以前、育休中のお金の話を書きましたが、今回は育休明けからのお金の話を簡単に書こうと思います。
〈関連記事〉
 育休中のお金の話
育休中のお金の話 ・復帰後の収入の話
育休手当は翌月払いや翌々月まとめ払いなどのパターンがありますが、復帰後の給料も勤め先によって異なります。私の場合は翌月払いになりますので、復帰月に給料の支給はなく、翌月に稼働日割での支給になりました。
例えば、2月に復帰の場合、2月は勤め先からの給料はなく2月働いた稼働日分、3月に支給されるという感じです。もちろん2月は1月分の育休手当が支給されますので、収入が途切れることはありませんでした。
・追加手当の話
これは勤め先の制度を確認して欲しいのですが、扶養手当や子ども手当を制度化している場合があります。私の会社では数年前に扶養手当が廃止されて子ども手当に統一されました。ですので、18歳未満の子ども1人あたりいくら、といった手当が給料に加算されます。会社によっては、子育てサポートをしてくれる制度があったりしますので、勤め先の制度はしっかり理解しておくと良いと思います。
・可処分所得増加の話
育休復帰後に大きく変わったと感じたのは住民税です。
住民税は前年の収入に応じて、6月に見直されますね。育休中は給与所得はありませんので、その分年収が下がっています。育休の期間や取得したタイミングによりますが、収入が減った分、もちろん住民税は下がります。毎月数万円単位で効いてきますので素直に嬉しいです。
あと年収が下がる分、保育料も変わってきます。今は国の政策で3歳児クラスから保育料無償化になりましたが、その年齢に満たない場合は第一子が満額、第二子が半額、第三子以降無償というのが一般的です。もちよん自治体によっては第一子から無償化されていたり、第二子から無償化だったりと違いはありますので、この辺はご自身がお住まいの自治体の制度をご確認ください。とはいえ、基本的に保育料は世帯収入に応じた支払いになりますので、これも毎月数万単位で効いてきたりします。
住民税と保育料の減額だけで、もちろん各ご家庭の収入状況にもよりますが、数万円、数十万円以上の支出を減らすことができます。
・ちょっと悲しいこと
育休中を含めて恩恵を受けられなかったのは年末調整ですね。収入がなく所得税、住民税を払っていないので当然なのですが、各種控除、特に住宅ローン控除が受けられないのはちょっと損した気分になります。
・気をつけた方がいいこと
私はふるさと納税をしていなかったので、育休前から気にしていなかったのですが、ふるさと納税も収入に応じての扱いになりますので、もし妊娠が発覚したら、出産予定日と育休取得による収入減を計算して、納税額を見極めないといけないのでご注意ください。せっかく節税している(正確には税金は支払うけど返礼品をもらっている)のに、過剰に納めるのはもったいないですからね。
☆育休のお金のポイント☆
育休中
○給料は発生しない
○育休手当が支給される
・賃金の67%(半年後から50%)
・育休手当は非課税扱い
・健康保険料や年金保険料免除
・ボーナスは支給される(勤め先の制度確認要)
復帰後
○育休手当⇒給料になるので収入は途切れない
○勤め先によっては追加手当がある
○住民税、保育料が下がる
注意事項
○年末調整の恩恵が受けられない(或いは減る)
○ふるさと納税はその年の収入状況を見極めて行う
簡単に書きましたが、「いざ育休をとろう!」と思ったときに育休期間と復帰後の収入シュミレーションをしておけば、安心して子育てに向き合うことができますのでご参考にしてくださいね。